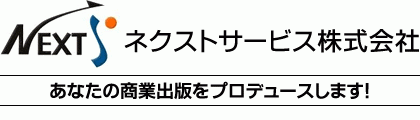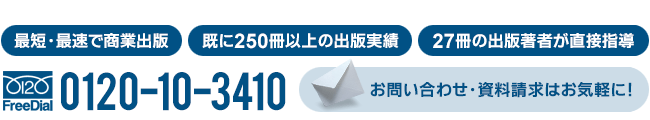伝わるビジネス書が書ける8つのルール。
この「伝わる」というのが大事です。
最終的には読者に伝わるということですが
ここではまず編集者に伝わると思ってください。
その前段階としてコーチやOBOG・同期など
自分以外の人に伝わる文章ということです。
1つ目はおいしいネタは先に出すことです。
読んでもらえなければ意味がありません。
皆さんのコアコンテンツそしておいしいフレーズを
1行目2行目3行目に書いてください。
推理小説は最後に犯人が書かれており
最後まで読んでもらうことを前提に構成されています。
しかし、ビジネス書は頭から読んで面白くなければ最後まで読んでもらえません。
2つ目はうまい文章でなく分かりやすい文章を書くことです。
ビジネス書や実用書に名文は必要ありません。
自分で良いと思う文章は独りよがりで読者を迷わせる文章と言われます。
では分かりやすい文章とはどういう文章なのでしょうか。
3つ目はメールを書くように文章を書くことです
メールがうまく書ける人は文章もうまく書けます。
今ならFacebookやTwitterのような短文です。
実際ビジネス書や実用書は短文の集まりです。
4つ目は文章の7割をたとえ話で組み立てることです。
たとえ話とはご自身の体験や事実の引用です。
ちなみに体験談は自分の体験でなくても構いません。
友達や親の体験でも良いですし
私はホリエモンや松下幸之助さんの体験なども書いています。
そうすると松尾だけが言っているのではなく
松下幸之助も言っているのだと読み手は納得せざるを得なくなります。
「私はこうやってうまくいきました」
「実はこの方法は松下幸之助さんの本を読んで実践したものです」
「こうしてみたら本当にうまくいき部下が動いたのです」と書きます。
孫正義さんや外国の有名な作家の引用でも良いです。
7割たとえ話で良いのです。
例えば「経済白書2024年版によると」というのも良いです。
「ベネッセ調べによると」などでも良いでしょう。
5つ目は1センテンス、1メッセージです。
1冊、1章、1見出し、1文すべて主張は1つです。
主張が変わったらもう1つ違う文章にしてください。
例えば「大切なことが3つあります」とあったら
1つ目の文章を書き2つ目はもう1つの文章にします。
「大切なことは7個あります」と1文で書くとどれが大切か分からなくなります。
もし7個あるなら1つの章に7個の項目を立てます。
6つ目は読みやすさは「見た目」で決まるということです。
読点は1行につき1つまで5行以上になったら改行してください。
とにかく読んでもらうことが大切です。
なるべく読点(、)でつなげず句点(。)で文を区切った方が良いです。
読点が多いと最初に何を書いたか分からなくなってしまいます。
「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」のように
読点を句点に変えられないか考えてみましょう。
文章がうまくなってきたら「しかし」や「だが」を外してみましょう。
逆接の接続詞を外しても文脈で読めるなら不要です。
「しかし」が多いと結局何が言いたいか分からなくなります。
7つ目は共感が7割意外性が3割です。
共感できる内容が7割意外性のある内容が3割ぐらいが良いということです。
これが逆だと「この人の言うことは自分と全然違う」と思われてしまいます。
私の本は8割が共感でき2割が「なるほど」となるように意識しています。
「松尾さんの本はすごくしっくり読めました」
「松尾さんの考えは私にすごく似ていて共感を覚えました」と言われます。
私は大衆に寄せて書いているからです。
多くの人が思うようなことを書かないとついてこられないのです。
「皆さんもそうですよね私もそうでした」
「ただ実はこのように工夫したらうまくいったのです」
これが伝えたかった意外性の2割や3割の部分です。
1行目から「挨拶はするな無礼であれ」などと書いたら「おいおい」と思うでしょう。
挨拶や礼儀は大切ですがそれだけで良いのでしょうか。
もしそれで良いならほとんどの人は成功しているはずです。
実は挨拶をしないで営業が取れる人も世の中にはいるのです。
「ここを知りたくないですか」と問いかけます。
皆が思っていることが7割から8割
そして2割がオリジナルまたは常識を覆すことです。
8つ目は書きやすいところからまず書いてみることです。
書けば書くほど書きたいことが見つかります。
1章目の最初の項目から書く必要はありません。
「これなら書ける」というところから書いていってください。
順番は本にするときに考えれば良いのです。
書いていくうちにだんだん書き慣れてきます。
この「伝わる」というのが大事です。
最終的には読者に伝わるということですが
ここではまず編集者に伝わると思ってください。
その前段階としてコーチやOBOG・同期など
自分以外の人に伝わる文章ということです。
1つ目はおいしいネタは先に出すことです。
読んでもらえなければ意味がありません。
皆さんのコアコンテンツそしておいしいフレーズを
1行目2行目3行目に書いてください。
推理小説は最後に犯人が書かれており
最後まで読んでもらうことを前提に構成されています。
しかし、ビジネス書は頭から読んで面白くなければ最後まで読んでもらえません。
2つ目はうまい文章でなく分かりやすい文章を書くことです。
ビジネス書や実用書に名文は必要ありません。
自分で良いと思う文章は独りよがりで読者を迷わせる文章と言われます。
では分かりやすい文章とはどういう文章なのでしょうか。
3つ目はメールを書くように文章を書くことです
メールがうまく書ける人は文章もうまく書けます。
今ならFacebookやTwitterのような短文です。
実際ビジネス書や実用書は短文の集まりです。
4つ目は文章の7割をたとえ話で組み立てることです。
たとえ話とはご自身の体験や事実の引用です。
ちなみに体験談は自分の体験でなくても構いません。
友達や親の体験でも良いですし
私はホリエモンや松下幸之助さんの体験なども書いています。
そうすると松尾だけが言っているのではなく
松下幸之助も言っているのだと読み手は納得せざるを得なくなります。
「私はこうやってうまくいきました」
「実はこの方法は松下幸之助さんの本を読んで実践したものです」
「こうしてみたら本当にうまくいき部下が動いたのです」と書きます。
孫正義さんや外国の有名な作家の引用でも良いです。
7割たとえ話で良いのです。
例えば「経済白書2024年版によると」というのも良いです。
「ベネッセ調べによると」などでも良いでしょう。
5つ目は1センテンス、1メッセージです。
1冊、1章、1見出し、1文すべて主張は1つです。
主張が変わったらもう1つ違う文章にしてください。
例えば「大切なことが3つあります」とあったら
1つ目の文章を書き2つ目はもう1つの文章にします。
「大切なことは7個あります」と1文で書くとどれが大切か分からなくなります。
もし7個あるなら1つの章に7個の項目を立てます。
6つ目は読みやすさは「見た目」で決まるということです。
読点は1行につき1つまで5行以上になったら改行してください。
とにかく読んでもらうことが大切です。
なるべく読点(、)でつなげず句点(。)で文を区切った方が良いです。
読点が多いと最初に何を書いたか分からなくなってしまいます。
「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」のように
読点を句点に変えられないか考えてみましょう。
文章がうまくなってきたら「しかし」や「だが」を外してみましょう。
逆接の接続詞を外しても文脈で読めるなら不要です。
「しかし」が多いと結局何が言いたいか分からなくなります。
7つ目は共感が7割意外性が3割です。
共感できる内容が7割意外性のある内容が3割ぐらいが良いということです。
これが逆だと「この人の言うことは自分と全然違う」と思われてしまいます。
私の本は8割が共感でき2割が「なるほど」となるように意識しています。
「松尾さんの本はすごくしっくり読めました」
「松尾さんの考えは私にすごく似ていて共感を覚えました」と言われます。
私は大衆に寄せて書いているからです。
多くの人が思うようなことを書かないとついてこられないのです。
「皆さんもそうですよね私もそうでした」
「ただ実はこのように工夫したらうまくいったのです」
これが伝えたかった意外性の2割や3割の部分です。
1行目から「挨拶はするな無礼であれ」などと書いたら「おいおい」と思うでしょう。
挨拶や礼儀は大切ですがそれだけで良いのでしょうか。
もしそれで良いならほとんどの人は成功しているはずです。
実は挨拶をしないで営業が取れる人も世の中にはいるのです。
「ここを知りたくないですか」と問いかけます。
皆が思っていることが7割から8割
そして2割がオリジナルまたは常識を覆すことです。
8つ目は書きやすいところからまず書いてみることです。
書けば書くほど書きたいことが見つかります。
1章目の最初の項目から書く必要はありません。
「これなら書ける」というところから書いていってください。
順番は本にするときに考えれば良いのです。
書いていくうちにだんだん書き慣れてきます。
- 1,ビジネス書はドンドン薄っぺらくなっている!(商業出版の裏側)
- 2,今の人たちは本を読まない|スマホネイティブの真実
- 3,人の悩みの数だけ本になる|出版の極意
- 4,「実は誰でも出版できる裏ワザ」三角形の法則
- 5,「三角形の法則」を使ってベストセラーになった成功事例
- 6,一般人が商業出版する「立ち位置チェンジの法則」
- 7,スターバックスが日本でテレビCMを打たないわけ|本の威力
- 8,出版の現実「85%は本屋に流通しない自費出版」
- 9,商業出版の現実「商業出版をしたければ出版社に対して企画書を作るべし」
- 10,商業出版は投資ビジネス|その理由と実態
- 11,モノが売れない3つの理由|こうやってモノを売れ!
- 12,書籍が解決する3つのこと|こぞって出版する理由
- 13,ミスマッチのないお客様を引き寄せる「バイブル商法」のススメ
- 14,仕掛け(プル型)営業の黄金パターン|ミスマッチのないお客様を引き寄せろ
- 15,出版でビジネスが加速する3つの理由
- 16,起業家や社長が出版するメリット
- 17,商業出版の現実「無名でも出版できる」
- 18,商業出版の現実「出版経験0だと著者になりやすい」
- 19,なぜKindle出版すると商業出版しにくくなるのか?
- 20,短期間で25冊の本を出版できた理由
- 21,人々が本を買う理由は●●のため|ビジネス出版ノウハウ
- 22,今の時代に●●なコンテンツはNG|ビジネス出版ノウハウ
- 23,人は欲や快楽を満たすために●●を買う
- 24,あなたの当たり前がお金になる|ビジネス出版ノウハウ
- 25,若者は●●が恐怖!?|ビジネス出版ノウハウ
- 26,社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった
- 27,誰でも本を書ける秘訣|未熟者が出版したら大ヒット!
- 28,本がヒットする法則|ビジネス書出版の極意
- 29,弱者だからできる出版で人生大逆転!
- 30,お金をもらって集客!?|出版ビジネス
- 31,環境を変えてお金持ちになるたった一つの方法
- 32,丸投げ命取り!あなたの大切な本のタイトル|現役ベストセラー編集者が伝授
- 33,悩まない!本のタイトルの作り方のコツ|現役ベストセラー編集者が伝授
- 34,未熟さを逆手にとって大ヒット!?|現役ベストセラー編集者が伝授
- 35,タイトル決めのポジションの取り方|現役ベストセラー編集者が伝授
- 36,編集者が萎える著者の●●|現役ベストセラー編集者が伝授
- 37,本を作ればあなたのすごさがわかる!
- 38,【爆速】プロ目線で作る最強出版術
- 39,●●にモテる方法|需要と供給のアンバランス
- 40,本を売るなら●●でバズれ!
- 41,【必見】ビジネス出版を成功させる方法を大公開!
- 42,【99%が知らない】誰でも出版できる秘密を明かします!
- 43,【悲報】こんな本は売れません・・・
- 44,【衝撃】アルバイトでも出版できた話
- 45,【知らないと損】儲かりたくない人は絶対見るな!
- 46,【9割が知らない】あなたの当たり前がお金になる
- 47,【意外】有名人の本は役に立たない?本当に必要な本は●●だった!
- 48,【ヤバすぎ・・】出版がもたらす驚異的な力
- 49,【スタバの秘密】来て欲しい客を集客するコツを教えます
- 50,【スピリチュアル→出版】本を出した成功者のリアル|小西昭生|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 51,【残念なお知らせ】●●な本の企画は通りません・・・
- 52,【誰でも】必ず出版できる極意を教えます
- 53,【経営コンサル→出版】本を出した成功者のリアル|藤原勝法|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 54,【集客できない人必見】商業出版は最強のブランディングツール
- 55,【必見!】理想の顧客を引き寄せる集客術
- 56,【すごい力】書店の本は魔法の集客ツール
- 57,【終活→出版】本を出した成功者のリアル|安藤信平|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 58,【絶対ダメ】今の時代にNGな商品の売り込み方
- 59,【金融コンサル→出版】本を出した成功者のリアル|川口幸子|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 60,【効果絶大】出版するとメディアに出演できる!?
- 61,出版する時にコレは絶対に言うな!
- 62,【料理人→出版】本を出した成功者のリアル|仲亀彩|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 63,売れる本は酷評が付きます
- 64,【誰でも】ビジネス実用書は出版すれば無名でも売れる
- 65,【LGBTQ→出版】本を出した成功者のリアル|宮川直己|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 66,【残念】●●は信用されません・・・
- 67,【誰でもできる】出版成功7つのルール
- 68,【ひとり社長→出版】本を出した成功者のリアル|小澤歩|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 69,今のままでは人生変わりません
- 70,やらないと後悔します・・・
- 71,【高校中退社長→出版】本を出した成功者のリアル|野沢琢磨|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 72,【必見!】著者にとって大切なこと|個人で本を出版する方法
- 73,【経営コンサル→出版】本を出した成功者のリアル|吉野創|個人で商業出版をするメリット
- 74,あなたが当たり前にできることが本になる|商業出版を個人でする方法
- 75,人の悩みの数だけ本になる|商業出版を個人でする方法
- 76,【楽天→出版】本を出した成功者のリアル|小林史生|個人で商業出版をするメリット
- 77,【勘違い】本は●●に向けて書かないと売れません
- 78,【驚愕!】ディズニーランドのアルバイトでも本を出せた!?|商業出版を個人でする方法
- 79,出版で会社員の年収が爆上げ|ネクストサービス出版スクール体験談|個人で商業出版をするメリット
- 80,【短所が強みに】黒歴史から本が生まれる!|個人で本を出版する方法
- 81,【意外】あなたにとって無価値な経験は本になります|個人で本を出版する方法
- 82,【チャンス】誰でも出版できる時代がやってきました!
- 83,ベストセラー作家になる方法を教えます
- 84,【大手執行役員→出版】本を出した成功者のリアル|金山亮|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 85,【悲報】その本、並ばずに返品されます・・・
- 86,●●をやると商業出版できなくなります・・・
- 87,【神主→出版】本を出した成功者のリアル|新井俊邦|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 88,【損します】自費出版はやめた方がいい理由
- 89,本を出したい人は必ず見ろ!
- 90,【ブランディング→出版】本を出した成功者のリアル|乙幡満男|ネクストサービス出版スクール卒業生
- 91,【※重要】本を書く人は●●に損をさせてはいけない!|商業出版を個人でする方法
- 92,【公務員→出版】本を出した成功者のリアル|仲里桂一|個人で商業出版をするメリット
- 93,そのプロフィールでは誰も信用しません・・・|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 94,【誰でも】人々があなたに感動するプロフィール作り|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 95,【システムエンジニア→出版】本を出した成功者のリアル|野中美希|個人で商業出版をするメリット
- 96,【残念】あなたのプロフィールは誰も読みません|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 97,黒歴史でもあなたの過去はブランドになります|商業出版を個人でする方法
- 98,【不動産コンサルタント→出版】本を出した成功者のリアル|前田浩司|個人で商業出版をするメリット
- 99,プロフィールの実績とセルフブランディングの方法|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 100,【プロフィール作り】実績なしでも人を惹きつける方法|個人で本を出版する方法
- 101,【看護師→出版】本を出した成功者のリアル|大軒愛美|個人で商業出版をするメリット
- 102,プロフィールは希少性を伝えろ!|商業出版を個人でする方法
- 103,【牧師→出版】本を出した成功者のリアル|石川有生|個人で商業出版をするメリット
- 104,【悲報】あなたが書きたい本は出版されません・・・|商業出版を個人でする方法
- 105,【完全攻略】出版までのロードマップを大公開!|個人で本を出版する方法
- 106,【オタク婚活→出版】本を出した成功者のリアル|横井睦智|個人で商業出版をするメリット
- 107,【知らないとヤバい】出版社が振り向く本のタイトルの作り方|商業出版を個人でする方法
- 108,売れる本はタイトルだけで内容がわかる|商業出版を個人でする方法
- 109,【着物→出版】本を出した成功者のリアル|上杉惠理子|個人で商業出版をするメリット
- 110,【誰でもできる!】本のタイトルの作り方のコツをプロが伝授|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 111,ターゲットを会社員にしないと出版できません|商業出版を個人でする方法
- 112,【数学→出版】本を出した成功者のリアル|鈴木伸介|個人で商業出版をするメリット
- 113,これを知らないと出版できません・・・|kindle・Amazon電子出版はやめなさい!商業出版であなたも著者に
- 114,出版するためのキーマンを捕まえろ!|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 115,【FP・社労士→出版】本を出した成功者のリアル|高伊茂|個人で商業出版をするメリット
- 116,あなたの本が売れるか見極める方法を出版のプロ解説|個人で本を出版する方法
- 117,誰でも本を書ける秘密を教えます|個人で本を出版する方法
- 118,【ウェブ制作→出版】本を出した成功者のリアル|芝田弘美|個人で商業出版をするメリット
- 119,出版社で通る企画書の作り方をプロが伝授|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 120,ベストセラー本の企画書を大公開!|商業出版を個人でする方法
- 121,【資産形成→出版】本を出した成功者のリアル|濵島成士郎|個人で商業出版をするメリット
- 122,ノウハウ型ビジネス本の書き方をプロが伝授!|商業出版を個人でする方法
- 123,出版成功者が親身に教えてくれる|ネクストサービス出版スクール体験談|個人で商業出版をするメリット
- 124,自己啓発本の書き方をプロが伝授!
- 125,1冊目を全力投球したら大成功|ネクストサービス出版スクール体験談|個人で商業出版をするメリット
- 127,LGBT当事者が激白「職場と差別と向き合い方」|個人で商業出版をするメリット
- 126,【※重要】ビジネス本の「はじめに」の書き方を教えます|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 128,ビジネス書の鉄則8つのルール|商業出版を個人でする方法
- 129,【必見】企画書にデータを入れて信頼を勝ち取れ!|商業出版を個人でする方法
- 130,【コンビニ経営→出版】本を出した成功者のリアル|長瀬環さん|個人で商業出版をするメリット
- 131,【営業マン→出版】本を出した成功者のリアル|上實貴一さん|個人で商業出版をするメリット
- 132,【弁護士→出版】本を出した成功者のリアル|保坂 康介 さん|個人で商業出版をするメリット
- 133,出版は誰でもデキる!一般人が出版して年収を3倍にする方法
- 134,【出版する方法】一般人が本を出すためには何をすればいいのか?
- 135,自費出版をすると大損します|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 136,出版したら印税はいくらもらえる?|個人で本を出版する方法
- 137,【必見】実績がなくても本は出せる!?|個人で本を出版する方法
- 138,【9割が知らない】無名でも本は売れる!?|kindle・Amazon電子出版はやめなさい!商業出版であなたも著者に
- 139,【誰でも】本を出版するとメディア出演ができる!?|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 140,【集客の裏技】商業出版で誰でも新聞広告!|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 141,【最高の恩返し】あなたが本を出すと喜ぶ人がいる|個人で本を出版する方法
- 142,【出版で逆転!】Fラン底辺が社会で生き残る唯一の方法|個人で本を出版する方法
- 143,【出版で人生が変わった】ブラック企業の会社員の年収が2倍なった!|個人で本を出版する方法
- 144,普通は絶対に会えない人と友達になれます!|個人で本を出版する方法
- 145,【出版の真実】文章が書けなくても本は出せます|商業出版を個人でする方法
- 146,稼げないフリーランスが出版で大成功した話|個人で本を出版する方法
- 147,【出版が心配】Amazonレビューの低評価が怖い!|商業出版を個人でする方法
- 148,【絶対やめろ!】電子出版をすると後悔します|kindle・Amazon電子出版はやめなさい!商業出版であなたも著者に
- 149,【必ず見て!】本のタイトルに会社名を勝手に使って大丈夫?|商業出版を個人でする方法
- 150,ディズニーランドのアルバイトが出版して大ヒット!|商業出版を個人でする方法
- 151,【出版したい人】新人だからこそ本をだせ!|商業出版を個人でする方法
- 152,【LGBTQ】コンプレックスを逆手に本を書くと売れます!
- 153,【経済メディア→出版】本を出した成功者のリアル|工藤 浩義さん|個人で商業出版をするメリット
- 154,【サラリーマン投資→出版】本を出した成功者のリアル|松田 二朗さん|個人で商業出版をするメリット
- 155,【クリスチャン経営者→出版】本を出した成功者のリアル|野田 和裕さん|個人で商業出版をするメリット
- 156,【完全版】出版をするならコレを見ろ!|商業出版を個人でする方法
- 157,【タワマン理事→出版】本を出した成功者のリアル|竹中信勝さん|個人で商業出版をするメリット
- 158,【心理カウンセラー→出版】本を出した成功者のリアル|片田智也さん|個人で商業出版をするメリット
- 159,【ひとり代理店→出版】本を出した成功者のリアル|小宮絵美さん|個人で商業出版をするメリット
- 160,【ひとりメーカー→出版】本を出した成功者のリアル|マツイシンジさん|個人で商業出版をするメリット
- 161,【※極秘】出版社が何社も手を挙げた本番プレゼン「個人で商業出版する秘訣」
- 162,【楽天→出版】本を出した成功者のリアル|ダニエル社長|個人で商業出版をするメリット
- 163,【プロが教える】誰でも商業出版ができる方法|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 164,電子出版をやってはいけない理由をプロが解説!|kindle・Amazon電子出版はやめなさい!商業出版であなたも著者に
- 165,【潜入】老舗出版スクールのガチ本番オーディション「大手出版社が続々と登場!」
- 166,出版することによって印税生活ができる?|個人で本を出版する方法
- 167,実は無名でも商業出版で本を出すことができます|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 168,【商業出版】本を書く時に編集者から100%ダメ出しを食らう人|商業出版を個人でする方法
- 169,【商業出版】文章が苦手でも本を出せる!?|個人で本を出版する方法
- 170,ビジネス著者になって年収を3倍にする方法を教えます!|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 171,本を出すことによって人生が変わった人|個人で本を出版する方法
- 172,商業出版すれば有名人になれる!?|自費出版はやめなさい!商業出版のススメ
- 173,【実はおいしい】商業出版は「炎上したもん勝ち」!?|商業出版を個人でする方法
- 174,出版が“採用ブランディング”になる時代―優秀な人材を惹きつける方法
- 175,【出版でテレビに出まくれる?】出版→新聞→ラジオ出演→テレビ出演…連鎖ブランディング事例
- 176,本を出すだけで単価3倍!高額商品を売れるようになるブランディング戦略
- 177,【出版の極意】編集者に嫌われる著者・好かれる著者の決定的違い
- 178,【持ち込み企画で出版は余裕か?】3ステップで出版社が動く!”勝てる企画書”マニュアル
- 179,出版業界の印税のリアルを全部話します
- 180,「この本がなければ今の自分はいない」人生を動かした3冊とは?
- 181,【衝撃】ONE PIECE作者の年収●●億円!人気漫画家の年収ランキングTOP10
- 182,【※特別公開】出版社が殺到したリアル本番プレゼン|商業出版を勝ち取ったリアル映像
- 183,編集者はここを見ている!出版を勝ち取るための原稿術
- 184,【共感を与える】ダメだった自分をさらけ出すと、本は読まれる!
- 185,【読まれる本の書き方】最初の一文で心をつかむ執筆術とは?
- 186,【ビジネス書の書き方】売れる著者が実践している8つのルール
- 187,【出版副業のリアル】印税だけで年収300万円も可能!?
- 188,【AI時代の出版論】本はもういらない?編集者は不要?プロが本音で語る未来
- 189,【※要注意】出版詐欺の手口を全公開!あなたも狙われているかも!?
- 190,【出版ドリーム】印税2億円! ベストセラー作家たちの驚きの収入を公開!
- 191,【金持ち父さん貧乏父さん】ネットワークビジネスの経典?世界的ヒットの秘密
- 192,大手出版社が集結!出版スクール本番オーディションの裏側
- 193,【無名でも出版できる】ディズニーランドのアルバイトが本を出した話
- 194,無名な人が電子出版をすると後悔します
- 195,【必読】出版のプロが勧めるお金持ちになる投資本6選
- 196,【※要注意】自費出版は情弱ビジネス!?その裏側を暴露
- 197,出版は特別じゃない!普通の人がヒット本を出す方法
- 198,小泉進次郎が総理になったら…小泉構文が本になる!?
- 199,【ブランド戦略】インフルエンサーや起業家はなぜ出版するのか?
- 200,【警告】自費出版の罠!著者が知らない高額コストの真実
- 201,商業出版したらすぐにやるべきこと!売れる著者が必ずやっていること
- 202,売れる本は著者が動く!成功者が実践する出版PR術
- 203,【日本のコミック】発行部数&印税ランキングTOP5
- 204,【情弱ビジネス】出版詐欺の実態を暴露!
- 205,【警告】あなたの文章が伝わらないのは「抽象的すぎる」のが原因です
- 206,【8対2の黄金比】読者が食いつく本の書き方を出版のプロが伝授!
- 207,【出版の裏側】プロが教える売れる本の作り方
- 208,【出版したい人必見】3大テーマで本をヒットさせる方法
- 209,【億稼ぐ営業力】高市早苗に見習う交渉術|起業家・サラリーマンの処世術
- 210,本を出すだけで節税に?出版が会社の経費になるカラクリ
- 211,出版で人生が変わる?本による集客は良いことだらけ!
- 212,【出版初心者チャンス】処女作が一番売れる本当の理由をプロが解説
- 213,【出版で成功した人】本を出したらNHK出演までつながった話
- 214,出版は最強の名刺!お金持ちの心をつかむ最強戦略
- 215,【読者に刺さる文章術】伝わる文章に共通する唯一のコツ
- 216,【リアルな声】本を出して変わった仕事と人生
- 217,【悲報】自費出版は書店に並びません・・・
- 218,【ガチ本番】出版スクールオーディションのリアルな裏側
- 219,【出版の威力】本を出したら年収が2倍になった理由
- 220,田中角栄は「本」を出して総理になった|出版で人生が激変した実例
- 221,【採用】出版をすると優秀な人材を確保できます!
- 222,【営業ゼロ】本を出したら単価が「90分90万円」になった話